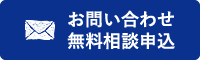- ホーム
- ブログ
ブログ
PTA講演会のうれしいご感想
2021/07/02
講演会終了後、主催者様から頂いた御感想です。
今日はとても有意義な時間をありがとうございました。
お迎えに来られた保護者の方から
「あっという間だった!!」
「すごく面白かった!」
「私こんなタイプだったよ!」
「子どもは創像で、私は堅実だったから、わけわからんはずやわ!!」
「今日は、反省することばかり。いろいろ言いすぎてる。今日の日のことを忘れないように折り紙の鶴を
見えるところに貼っておきます。」
「とても親しみやすい先生だった。友達と話してるみたい」
など、たくさん嬉しい言葉が届きました。
私たち役員の中でもタイプが分かれて、大いに盛り上がりました。
リアルではなかなか繋がりにくい毎日ですが、こんな形で皆さんとつながれたことが本当に有意義で感動しています。
そんなきっかけを作ってくださった上田先生には感謝しかありません。
今回オンライン(Zoom)を初めて導入するという事で、役員一同、ほぼ初心者でしたが、
講義内容以外のことでも何度も親身に相談にのってくださり、一つずつ不安を解決し、
オンライン講演会をやってみよう!と背中を押していただけたと思います。
本当にありがとうございました。
そして私たち自身も、充電しながら(笑)そのままの子どもたちを受け止め、
一緒に過ごす時間を楽しでいけたらと思います。

企業の一室で、プレ幼稚園をすることになりました
2021/06/30


我慢できない子どもをどうしたらいいのか??
2021/06/08


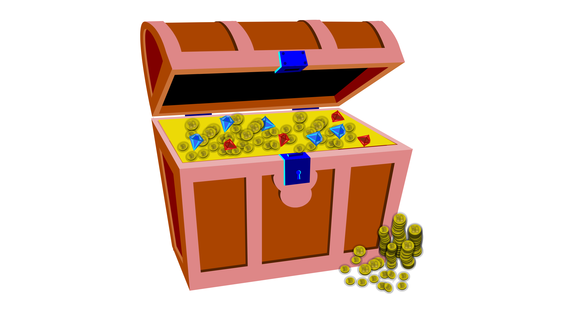
何も言わずに待てますか?
2021/05/26



子ども主体の保育の難しさ
2021/05/21


雨の日の保育
2021/05/17

保育士の顔
2021/05/13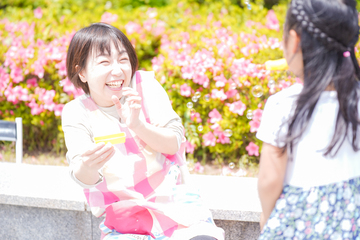

保育士さんの急なご都合やケガ、病気など、1週間だけうちの園を助けてほしい・・・
そんなご依頼におこたえし、
保育園・幼稚園の選ばれ方
2021/05/10保育園・幼稚園は、どこを見て選べばいいのですか?

- 園の方針(ご家庭の方針と合っているのか?)遊びが多い園の方が、子どもは対応しやすい
- 保育室の清潔さ(トイレが汚いと、ウイルス系の病気が流行りやすい傾向にあり)
- 外遊びの時間の長さ(子どもは、自由遊びの中で学び考える事が増える)
- 家からの距離(通園バス経路など)
- 預かりサービス
- 給食やお弁当の有無
- 課外活動の内容
人見知り??
2021/04/30
ゆっくりフライデー カウンセラーの日でした。
今年度で、5年目になります。
昨年度からコロナの影響で、晴れの日は、園庭でお子様と遊びながら子育ての悩みや世間話をして、
日々の子育てストレスを少しでも軽減できるようにお手伝いをしています。
新年度になり、1歳児さんが多く訪ねて来てくださいますが、
初めての場所、初めての先生、初めてのお友達に圧倒されて、
お子さんがなかなか本調子で遊ばず終わってしまうことも・・・( ;∀;)
お母さんの気持ちとしては、「せっかく連れてきたんだから遊んでほしい・・・」
ですが、
お子様の気持ちは、「初めての場所で緊張するよ・・・」なんですよね。
そんなお子様でも、1時間もすれば、すこーーーしずつ慣れてきて、少しずつ遊び始め、
今日の最後は、ダイナミックに泥にまみれて遊ぶ姿が見られました。
今まで、水も使ってダイナミックにお砂場で遊んだことはなかったけど、様々なものを感じて、お友達が楽しそうに遊んでいるのを見て
「わたしも!!」
と、思ってくれたんですね(^^♪
良かった良かった💛
次来た時は、またふりだしに戻るけど、慣れるのはきっと早くなっていくでしょうね。
保育士さん・幼稚園の先生の新人研修とは・・・???
2021/04/28ズバリ!!!!
職人のように、
「見て学べ!!!」
「分からなかったら、聞く」
「実践あるのみ!!」

離職にもつながっているなんて、、、
(初めて知った時は、私も驚きました!!!)素晴らしい園が、より良い園になりますように。
-
 保育業界が淘汰されていく時期がきました
保育業界もそろそろ改革時期になってきました。数年前から、子どもの数が減って、保育園の数も減ってくると言われてい
保育業界が淘汰されていく時期がきました
保育業界もそろそろ改革時期になってきました。数年前から、子どもの数が減って、保育園の数も減ってくると言われてい
-
 怒涛の4月を過ごすポイント!
世間では、GWに入りましたが、保育業界は、暦通りなのでひと息つくには、あとわずかですね!!怒涛の4月を乗り越え
怒涛の4月を過ごすポイント!
世間では、GWに入りましたが、保育業界は、暦通りなのでひと息つくには、あとわずかですね!!怒涛の4月を乗り越え
-
 今までにない!!主任育成プログラムが始まります!!
4年程前より、保育士のメンターとしての活動を始めましたが、幼稚園・保育園へサポートに行くと、現場保育士を育成す
今までにない!!主任育成プログラムが始まります!!
4年程前より、保育士のメンターとしての活動を始めましたが、幼稚園・保育園へサポートに行くと、現場保育士を育成す
-
 コーチングをベースにしたマンツーマンの主任育成研修
昨年度より作成しており同じ想いをもつ同志にも恵まれて、完成した「保育マネージャー育成プログラム」従来のテンプレ
コーチングをベースにしたマンツーマンの主任育成研修
昨年度より作成しており同じ想いをもつ同志にも恵まれて、完成した「保育マネージャー育成プログラム」従来のテンプレ
-
 主任が自ら動くようになる研修
東京から始まった新たな取り組み「保育主任研修」5月~7月までの3ヶ月保育園を8園運営している株式会社様の4園の
主任が自ら動くようになる研修
東京から始まった新たな取り組み「保育主任研修」5月~7月までの3ヶ月保育園を8園運営している株式会社様の4園の